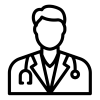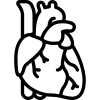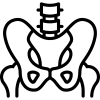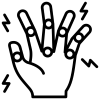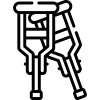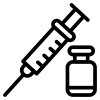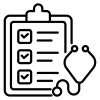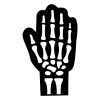調布そわ内科・整形外科の曽和裕之です。
今回は、身近ですが、放置すると怖い疾患である高血圧症についてお話しします。
高血圧症は「沈黙の病」や「サイレントキラー」とも呼ばれ、自覚症状がほとんどないまま進行する疾患です。血圧が高い状態が続くことで、心臓や血管に負担がかかり、動脈硬化をはじめとするさまざまな合併症を引き起こします。
日本において高血圧性疾患の推計患者数は4,300 万人(高血圧治療ガイドライン2019より)であり、そのうち実際に治療を受けているのは約1,609 万人(厚生労働省「患者調査」より)と報告されています。
生活習慣病の中でも最も身近でありながら、放置することで将来の健康に大きな影響を与える可能性があります。
本記事では、高血圧症の基本的な知識と、当院で行える検査・治療についてご紹介いたします。
高血圧とは
高血圧とは当然のことながら血圧が高い状態のことを言いますが、その定義を知っている人は少ないのではないでしょうか。
6年ぶりにガイドラインの改定がありました。2025年高血圧症ガイドラインによると以下のような基準を平均的に上回る場合に、高血圧症としています。
家庭血圧 135/85 mmHg
診察室血圧 140/90 mmHg
以前までは年齢により降圧目標が異なりましたが、今回の改定により降圧目標は年齢によらないこととなりました。
【降圧目標】
家庭血圧 125/75 mmHg
診察室血圧 130/80mmHg
家で測る血圧に比べて、診察室で測る血圧の方が高めに出ることが多いため、このように基準に差があります。血圧の差が出る理由は主に以下のようなものがあると私は考えています。
>安静時の測定にはなりにくい
医療機関まで歩いてきて、到着してすぐに測定することが多い
>周りに人がいる環境で測る
緊張してしまう
そのため、健診などで高血圧が疑われた場合は、まずはご自宅で血圧をつけていただくことが重要になります。
測り方の推奨としては、起床時と寝る前の2回測定になります。起床時は起きて1時間以内、トイレをすませ、服薬・食事前に測定します。就寝前は、入浴後1時間以上時間をあけて測定します。いずれも1-2分安静にしてから測ります。
しかし、人によっては、1日2回必ず血圧を測るようにすることがストレスになってしまうこともあるかと思います。その場合には、まずは1日1回、気が向いたときに測ることで、だいたいの傾向を見る、というのでもよいかと思います。その後1日2回血圧測定すべきかどうかは相談していきましょう。
高血圧の原因には大きく二つあります。
患者さんの背景や必要に応じて検査で調べております。
- 本態性高血圧:生活習慣(塩分過多、肥満、運動不足、ストレスなど)や加齢や遺伝的要因が関与し、原因を特定できないもの(全体の約9割)。
- 二次性高血圧:腎臓やホルモンの異常など、特定の疾患が原因となるもの。血液検査や画像検査で診断をおこない、原因疾患の治療もおこないます。
放置するとどうなる?
高血圧を放置すると、血管の内側に強い圧力がかかり続け、血管が硬くもろくなる動脈硬化を進行させます。その結果、以下のような重大な病気を引き起こす可能性があります。
- 心筋梗塞・狭心症
- 心不全
- 脳卒中(脳出血、脳梗塞)
- 腎不全
- 大動脈瘤・大動脈解離
これらは命に関わる病気であり、日常生活に大きな制限をもたらすこともあります。
高血圧の症状は?
多くの方は症状を自覚しません。
しかし、進行し、合併症を発症すると次のようなサインが出ることもあります。
- 頭痛やめまい
- 胸の痛みや圧迫感
- 動悸や息切れ
- むくみ
これらの症状がある場合には、すでに心臓や血管に負担がかかっている可能性があります。
当院で行える検査について
高血圧症の診断や合併症の評価には、血圧測定だけでなく精密な検査が必要です。当院では次のような検査を行っています。
- 心臓超音波検査(心エコー)
心臓の動きや大きさ、弁の働きなどをリアルタイムに観察できます。高血圧で心臓に負担がかかると、心筋が厚くなったり、心臓の機能が低下したりするため、その評価に有用です。
- ABI(足関節上腕血圧比)
手と足の血圧を比較し、動脈硬化の有無を調べる検査です。末梢動脈疾患(PAD)の早期発見につながります。
- CAVI(心臓足首血管指数)
動脈の硬さを数値化できる検査です。年齢や血圧に左右されにくく、動脈硬化の進行度を客観的に評価できます。
- 頸動脈超音波検査
首の血管を観察し、動脈硬化による血管の狭窄やプラークの有無を確認します。脳梗塞のリスク評価にもつながります。
- ホルター心電図
24時間心電図を記録することで、不整脈の状況を把握できます。高血圧の方は不整脈を合併することも多く、精密な管理に役立ちます。
これらの検査により、単なる血圧の数字だけでなく、血管や心臓の状態を総合的に把握することが可能です。
治療の基本
高血圧治療の柱は「生活習慣の改善」と「薬物療法」です。
≪生活習慣の改善≫
- 減塩(1日6 g未満を目標)
- 野菜・果物を多く摂取し、バランスの良い食事(カリウムやマグネシウムの摂取)
- 適度な運動(ウォーキングなどの有酸素運動を30-60 分/日)
- 禁煙
- 適正体重の維持(BMI 25 kg/m2未満)
- 節酒(男性でビール 500 mL/日程度まで)
特に日本では醤油や味噌などの伝統的な調味料に塩分が多く含まれることもあり、アメリカやヨーロッパと比較しても日本人の塩分摂取量が多いことが知られています(欧米:8-10 g/日、日本 10 g前後/日)。
減塩食だけで血圧が低下することも多いので、一度塩分を中心として食生活の見直しをすることは非常に有用です。外来では減塩の一助となるようなチェックシートもお渡ししております。
≪薬物療法≫
生活習慣の改善だけで血圧コントロールが難しい場合、降圧薬を使用します。薬の種類はカルシウム拮抗薬、ARB、利尿薬、β遮断薬、α遮断薬、アルドステロン拮抗薬、ARNIなどがあり、患者さんの年齢・合併症・生活背景に応じて選択します。
私は患者さんの背景疾患に応じて、カルシウム拮抗薬とARBとβ遮断薬を中心に投薬設計を組むことが多いです。
これらの薬を単独で使うこともあれば、組み合わせて使うこともあります。複数の作用を取り入れることで、よりしっかりと血圧を下げることができます。
[合剤(配合剤)という選択肢]
最近では、2種類の薬を1つにまとめた「合剤(配合剤)」も広く使われています。
薬の数が減り、飲み忘れが少なくなることが最大のメリットかと思います。
「薬が増えて大変」と感じる方にとって、合剤は治療を続けやすくする大切な工夫です。当院でも患者さんの生活や合併症を考慮し、最適な組み合わせをご提案しています。
早期発見・継続治療の大切さ
高血圧は一度診断されても、治療を継続することで十分にコントロール可能な病気です。しかし「症状がないから大丈夫」と自己判断で薬を中断すると、重大な合併症を引き起こす危険が高まります。
定期的な血圧測定に加え、当院で行える各種検査を組み合わせることで、ご自身の血管年齢や心臓の状態を把握し、最適な治療方針を立てることができます。
まとめ
高血圧症は、日本人に非常に多い生活習慣病でありながら、自覚症状に乏しいため見過ごされがちです。しかし放置すれば、心筋梗塞や脳卒中といった重篤な病気を引き起こす可能性があります。
当院では、心臓超音波検査、ABI・CAVI、頸動脈超音波検査、ホルター心電図などを用いて、総合的に高血圧とその合併症リスクを評価しています。早期発見と適切な治療が将来の健康を守る第一歩です。
「血圧が少し高い」「家族に高血圧の人がいる」「健康診断で指摘された」――そのような方は、ぜひ一度ご相談ください。
循環器専門医が、安心できる診療体制でサポートいたします。