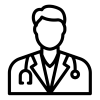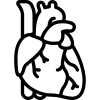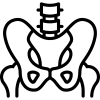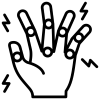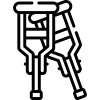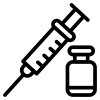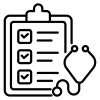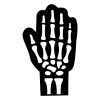▶ 心房細動
心臓の中の心房といわれる部位が十分な収縮をせず、けいれんするように細かく震えることで脈が不規則になります。動悸や不快感として自覚する場合もあれば、症状がない場合もあります。加齢に伴い心房細動は発症しやすくなりますが、肥満やストレスなどの生活習慣などによっても発症のリスクは高まり、日本では100万人の患者さんがいるといわれている決して珍しくはない疾患になります。症状以外に困ることとしては、心房細動が持続することで、心不全や脳梗塞を発症するリスクが高まることが知られています。薬やアブレーション治療により不整脈の根治を目指したり、リスクによっては脳梗塞予防として血液がサラサラになる薬を飲むこともあります。
▶ 徐脈性不整脈
脈がゆっくりになる不整脈の総称になります。心臓は全身に血液を送る役割を担っているので、脈がゆっくりになるとそれが不十分になり、心不全による息切れやむくみ、倦怠感などを認めます。心臓の筋肉に問題がある場合や、薬や電解質(カリウムなど)の影響の場合もありますが、不可逆的な問題である場合も多いため、その場合にはペースメーカーの手術を検討します。
▶ 期外収縮
心臓は一定のリズムで拍動をしていますが、時々期外収縮という予定外の拍動が見られます。健康な人でもストレスや疲れなどで起きる不整脈ですので、必ずしも治療が必要な不整脈とは言えません。ただし、期外収縮による動悸や不快感などの症状がある場合や、期外収縮が起こるような心臓の問題があったり、期外収縮が危ない不整脈に移行しうるような状態である場合には治療が検討されます。内服薬やアブレーション治療による介入を検討します。
▷ カテーテル アブレーション治療
不整脈は、異常な電気回路や一部からの異常な電気興奮によって生じますが、その異常な電気活動に対して、カテーテルを用いて焼灼や冷凍凝固等を行い、不整脈の根治を目指す治療になります。専門の病院での治療になりますので、必要に応じて適切なタイミングで治療可能な病院へとご紹介いたします。