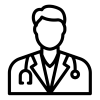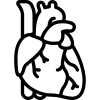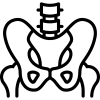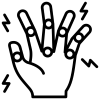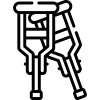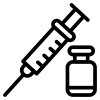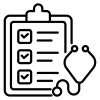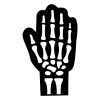▶ 急性腰痛症
いわゆるぎっくり腰です。重いものを持ち上げた時や急な姿勢の変化などで突然発症します。腰の関節やその周りの筋肉や靱帯が痛みの原因となることが多く、安静だけで治ることも多いですが、必要に応じて薬の内服や神経ブロック注射などを行うこともあります。
▶ 椎間板ヘルニア
背骨は椎骨という骨から成っていますが、骨の間には椎間板という軟骨があります。椎間板は椎骨同士のクッションの役目を担っていますが、外に突出する(ヘルニア)ことで近くにある神経や脊髄を圧迫して、痛みやしびれなどが生じます。保存療法(手術をしないこと)により約90%の人が改善するといわれています。リハビリも非常に有効です。
▶ 坐骨神経痛
坐骨神経という腰のあたりから足に伸びている神経が何らかの原因(椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症など)によって刺激されることで痛みやしびれを生じます。薬物療法やリハビリなどで、神経を刺激している原因にアプローチをします。
▶ 脊柱管狭窄症
椎骨にはトンネル状の構造(脊柱管)があり、その中を脳から続く神経の束が通っています。脊柱管の狭窄により神経が圧迫されると手足の痛みやしびれなどが生じます。歩き続けることが困難で、休み休み歩く必要が出てくることもあります。骨や靱帯の変性が原因で、薬物療法やリハビリ、手術の検討をおこないます。
▶ 骨粗鬆症、脊椎圧迫骨折
加齢や運動不足や女性ホルモンの低下などにより、骨がもろくなることを骨粗鬆症といいます。骨折の原因となり、椎骨がつぶれてしまうことがあります(脊椎圧迫骨折)。骨粗鬆症には内服薬以外にも、非常に有効な注射での治療(月1回や半年に1回など)もあり、患者さんの病状に応じて治療をご相談しております。
▶ 腫瘍(癌の転移など)や感染症
内臓の癌(がん)の転移など、脊椎に癌が転移することも知られています。また脊椎の感染症による腰痛などもあります。当院ではそのような疾患を見逃さないために他院でのMRI検査なども必要に応じておこなっております。手術や入院が必要な場合には適切に対応できる体制をとっていますので、安心してご相談いただければと思います。